注)患者本人が読むことはおすすめしていません。周囲にいる人がどのような点に留意して関わったらいいのかについて、個人的な意見を書いてあります。
[ad#cm]ボダの輝くところにお助けおじさん(取り巻き)あり
パーソナリティ障害関連を調べていたら出てきた「お助けおじさん」という単語。
パーソナリティ障害の人がその力を発揮する背景には、ほぼ必ず「お助けおじさん(おばさん)」などの存在がいるという趣旨の内容でした。
思い返せばそうだったと納得しながら、B群のパーソナリティ障害の方との人間関係に疲弊しながら心理学を学んできた身として、悩んでいる人に向けて知識の共有をできればと思い記事を書いていきます。
なぜ「おじさん」と命名されているのか?については、パーソナリティ障害の中でも特に若い女性に多いとされる境界性パーソナリティ障害の人は、女性として魅力的な場合が多く、そんな女性を守りたいというナイト的な役割を担う男性がうまくマッチングするらしいです。
もちろん、マッチングは男女に限りませんし様々なケースがあります。
「取り巻き」という表現の場合は性別で区別していませんが、「お助けおじさん」の場合は少なからず性的な魅力に惹かれた異性というニュアンスがあるが故の表現かと思います。
基本的にB群に分類されるパーソナリティ障害は対人操作性が高いので、周囲の人をコントロールするスキルに長けています。
お助けおじさんは「正義のヒーロー」になりたい
[ad#cm]「お助けおじさん」は多くの場合「善意の人」です。
…というよりも、「正義」に囚われやすい人である場合も多いです。
特に彼女を守るために戦うナイト的な役割を担っているケースでは、「女の子を守ってる俺かっこいい」みたいな感覚によって自分自身もエゴを養っているところがある、そういう傾向が強いです。
こういった人は正義感とか善意の名のもとに、パーソナリティ障害の人の人心掌握術にハマってしまいます。
「私はあの人によってこんなにひどい目にあっている。」
「こんなに不幸な境遇で…困っているの。助けて。」
という類の同情をひくような嘘の言動(だいたい事実を過剰に装飾しています)によって惹きつけられるというのが多くのパターン。
そして、「僕は○○ちゃんの味方だよ!」ということで、パーソナリティ障害の人の望む行動をとるんですね。
「○○ちゃん守ってる俺格好イイ!」と。
境界性パーソナリティ障害傾向をもつの人の内面
[ad#cm]パーソナリティ障害はその傾向によっていくつかの群にわけられています。
その中でもB群は対人操作傾向が強く他人を巻き込みます。
また、B群の中で自己愛性パーソナリティ障害や境界性パーソナリティ障害、演技性~など、複数の特徴を併せ持つようなタイプも多いというのが実態です。
境界性パーソナリティ障害や自己愛性パーソナリティ障害などのパーソナリティ障害の人は基本的に不安定な内面を抱えており、依存対象を求めます。また、不安定な内面ゆえに自分が安全・有利・優位ではなくなる事態をあらゆる手段を講じて避けようとする傾向が強くなります。
健康な人にとっては些細なことでも、「生きるか死ぬか」のような感覚がつきまとうような感覚で生きているのですね。境界性パーソナリティ障害の方がこの不安定さは顕著に行動に顕れます。
[ad#cm]「あらゆる手段」というのは、嘘でもなんでもかまわない、相手の都合をはじめとした道徳的なことは度外視しているということでもあります。まさに「溺れる者は藁をも掴む」という状態です。
そして、これはボーダー(境界性パーソナリティ障害)でよく見られる言動ですが、本人があまりに追い詰められるとリストカットなどで「自分を人質にして」周囲を脅し、自分の望む行動を取ることを期待することもあります。
俗に言う死ぬ死ぬ詐欺もそうですが、かまってもらえないなら死ぬ!というのが基本姿勢です。
その傾向が顕著だった女性と結婚した方は、打ち上げなど、その人が妻とは関わり合いの無い集団の中で過ごす時間になると必ずといっていい頻度で妻から「死にたい」という電話がかかってきて、暗い顔して帰宅していました。ちなみにその女性は教育業界では生徒にパワハラをすることで有名でした。
自殺の仄めかしなどは境界性パーソナリティ障害の診断をされる人によくみられる言動ですが、パワハラは自己愛性パーソナリティ障害によくみられる言動です。
よく「ボダからは逃げろ」と言いますが、巻き込まれると本当にものすごい消耗します。その影響は周囲の人間がトラウマやストレスを抱えて病気になるほどです。
操作性や攻撃性は防衛本能からくるので被害者意識が強い
[ad#cm]パーソナリティ障害は障害なので、普通の人なら「よくそこまでするよね」と感じるようなことが出来てしまいます。そういった過剰な行為を自分で思いとどまることが難しく衝動的にやってしまう、そういう障害です。
人格形成時点での不適切な関りにより不安感が強すぎて、生死に関わるような事態に直面したときに起こる脳の反応が日常レベルで頻発しているといわれています(「偏桃体が暴走している」などと言われていたりします)。
あらゆる問題となる言動も「防衛本能が暴走した状態」なのですが、対人関係における行動の実際は過剰防衛を通り越してかなり作為的・積極的に攻撃しているような状態になってしまうのがトラブルを頻発させてしまう原因です。
ですが、本人の本能的な感覚では「自分を守っている」という状態で、むしろ強く被害者意識を持っています。(実際、多くの場合は生育環境において被害者です)
[ad#cm]「そうしないといられない」状態で、ましてや自分に生じる不安を適切に処理することができません。そのため記憶までも変わってしまうことすらあります。筆者自身、診断付きのご本人と接してきて、自分で嘘と本当の区別がついているのかも正直疑問だと感じることが少なからずありました。
迫真の演技、というよりも、そういった演技は「不安が増幅された危機的状況が真実であるという思い込み」の結果なので、とても演技には見えない悲痛な相談に、心の優しい多くの人は共感し、「(実態としては)騙されて」しまいます。
境界性パーソナリティ障害の「かまって」を見分ける
[ad#cm]心理学の知識を得ることや人生経験を積むことによって、境界性パーソナリティ障害の人特有の「相談」や情緒の不安定さに違和感をおぼえることができるようになりますが、特に若年層で見分けるのは大変です。
10代~20代前半くらいの人間関係は、境界性パーソナリティ障害の人の影響を強く受けてボロボロになることも少なくありません。
特にボーダーな彼女と付き合ってしまった元彼氏の愚痴には壮絶な体験談が含まれていたりします。女性不信になるのも頷けます。ですがボーダーな彼女と付き合った過去を持つ男性にお伝えしたいのは、「その人がそもそも特殊です」ということです。
健康な女性は自分を人質にして言うことを聞かせようとしたりしません。
[ad#cm]<注意点として>
対人関係において、同情心、庇護欲、そういった感情が過度に刺激される「相談」を、そこまで親しくない距離の人にされた場合、警戒した方がいいです。
さらに、「○○が無くて困っている」など、そこからこちらが何かしてあげたくなるように誘導されるような話題があった場合、それはもう対人操作方法の典型例ですので上手に距離をとった方がいいでしょう。
境界性パーソナリティ障害、自己愛性パーソナリティ障害は、距離を詰めるスピードがやけに早いのが特徴の一つです。自他の境界が曖昧だからこそなのですが、これも見分けるための一つの指標になります。
これらのパーソナリティ障害はターゲットにロックオンした後はあっという間に「親友」「運命の人」のようなポジションにいます。
境界性パーソナリティ障害と自己愛性パーソナリティ障害は似ている
[ad#cm]境界性パーソナリティ障害と自己愛性パーソナリティ障害は共通するところも多く、専門家や医師でも正確な診断が難しいと言われています。
自己愛性パーソナリティ障害と診断するのは診察時間だけの短時間では難しい、ということもあり境界性パーソナリティ障害と診断する傾向にある、というのも実態のようです。
私個人は自己愛傾向が殆どない境界性パーソナリティ障害の方には今のところ出会ったことがありません。そのため記事には自己愛性パーソナリティ障害あるあるな言動も含まれてしまっています。その点はご了承ください。
自己愛性と比較すると、境界性の人は見捨てられ不安が強いです。そして、自傷行為や自殺未遂など衝動的な行動が目立ちます。
自己中心性や対人トラブル傾向は両方に共通しています。操作性は境界性の特徴とされていることが多いですが、人を利用しようとするという意味での操作性は自己愛性にもよくみられます。
治る?治らない?
[ad#cm]境界性パーソナリティ障害は若い女性に多いと言われています。それは治療によって症状が軽快していくことが多いからです。
しかし、自己愛性パーソナリティ障害の場合、治るとは一般的にあまり言われていません。むしろ歳を重ねるごとにひどくなるとすら言われています。その大きな違いは、本人が困って受診をすることがそもそもないからです。
これは個人的な見解ですが、おそらく「自分は価値のない人間だ」という感覚を見つめることができるかどうか、という点において、境界性パーソナリティ障害の場合はそれを見つめているがゆえにショックを受ける、困るから受診する、という流れがあります。
一方で自己愛性パーソナリティ障害の場合はその無価値感を無かったことにする傾向が強いため、変わることも変わる必要も本人の中ではないからなのではないかと思います(自己愛性パーソナリティ障害の中でも自分がそうであると認識できる比較的軽度な方もいらっしゃいますが)。
あなたにはあなたの人生があります。
相手の問題は相手の問題としてお返しして、皆様が健やかな日常を過ごせるように応援しています。
他にも自己愛性パーソナリティ障害や対人関係の悩みにまつわる記事をたくさん書いているので是非参考にしてみてください。
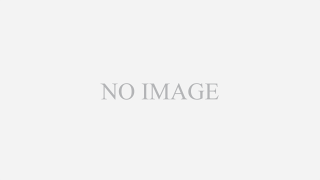
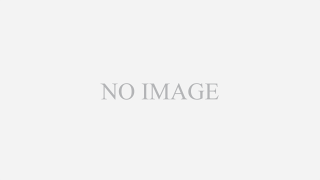
コメント